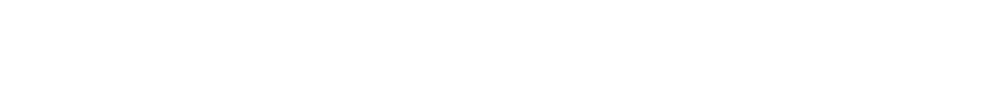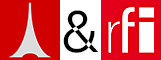Tonton Manu
2013年12月12日、Patrick PuzenatとThierry DechillyがManu Dibangoの80歳の誕生日に行われたフェスティバルを撮影しようと決めたとき、このパリでの撮影が、ロンドン、ニューヨーク、リオデジャネイロ、ドゥアラ、アビジャン、キンシャサ、そしてサンカレーへと続く国際的な旅の最初のステージになるとは想像もしていませんでした。そして冒険の最後には、映画『トントンマヌ』が公開される。
カメルーンの有名なサックス奏者兼バンドリーダーであるマヌ・ディバンゴと一緒に体験する映画の冒険を予想していなかった2人のフランス人監督、パトリック・プゼナとティエリー・デシリーは、2013年12月12日のアーティストの誕生日前後に始まったイベントに身を任せ、ホストの地球の四隅への旅を段階的に追っていきました。徐々にドキュメンタリー制作の構想が具体化していく…。
このようなプロジェクトの形式、リズム、意図はまだ決まっていません。当時のマヌ・ディバンゴは颯爽とした八面六臂の活躍ぶりで、そのオーラは多くのリクエストを集めていた。彼の叙事詩を古文書や解説書で再現するのではなく、彼の旅に同行し、観察し、耳を傾けることが大切なのです。カメラは、自分の豊かな運命について遠慮がちに明かす人物の、控えめな目撃者であり、時には相談相手にもなるのです。
マヌ・ディバンゴ、真摯な感情
2013年から2018年までの5年間、「トントンマヌ」は、記憶しているシンプルな男性の青春時代を、親密で愛らしい形で散策します。よくあることですが、本当のマヌ・ディバンゴは、会話や出会い、交流の中でその姿を現します。
ロンドンでは、BBCのジャーナリストから「ソウル・マコッサ」について聞かれたとき、彼の満面の笑みは、マイケル・ジャクソンとの論争についての終わりのない質問に答えることへの疲れを隠しきれない。Patrick PuzenatとThierry Dechillyは、何ヶ月にもわたって、笑い声だけでは隠しきれない真摯な感情を表現してきました。
彼の信頼を得ることで、尊敬されるアーティストであり、厳格なオーケストレーターであり、献身的な市民であり、ノスタルジックな家長である、本物のマヌ・ディバンゴの姿が浮かび上がってきます。世界的な成功が待ち受けていたハーレムのアポロでの最後の公演から40年後の2015年、ニューヨークで、彼は喉の痛みを半ば認めている。彼をこの伝説的なアメリカの劇場に連れて行った車の中で撮影されたこの短いシークエンスは、千のスピーチに値する。マヌ・ディバンゴは自分自身であり、観客を誘惑しようとはせず、自分の記憶の中に一人でいる。
サンカレーに戻る
彼が1949年に、いわゆる「海外のフランス」から来た小学生になったサルト地方のサン・カレーに戻ってきたときも、同じような感激がある。70年の歳月が流れ、手なずけなければならない新しい世界に迷い込んだ若きカメルーン人のイメージが、2010年代の気配りの行き届いたティーンエイジャーに語りかけることで、突如として脳裏に蘇ったのです。
彼が選んだ言葉は、数十年前に学友と共有していた価値観である、団結、寛容、寛大を呼びかけるものでした。枯れた声が感情を裏切り、マヌ・ディバンゴが白昼堂々とは見せたくない、ごく自然な悩みをこっそりと感じ取ることができます。
公私混同で固められたこの殻を突き破ることができるのは稀なことだった。この真実の瞬間は、彼の子供時代の学校で、植民地化が海や大洋を越えて運んできたアフリカの世代の亀裂を、力強くかつ繊細に描写しています。
マヌ・ディバンゴもその一人でしたが、彼はこの社会的・文化的特殊性を利用する方法も知っていました。いくつかの遺産から栄養を得て、彼は自分のアイデンティティを確立し、世界共通の言語を作りました。そのため、2016年のリオデジャネイロで、彼が若い頃から貪欲に受け入れてきたフランス語圏のスポークスマンの役割を担ったとしても、驚くことではありません。
また、彼の分身であるコンゴのピアニスト、レイ・レマと一緒にブラジルでシンフォニックなプロジェクトを立ち上げたことも驚きである。二人とも、本当の意味でのアフロ・プラネット・ミュージックの幕開けを目指して、常にキャンペーンを行ってきました。彼らの共通のメロディ・サイエンスが彼らを結びつけ、この共犯関係はパトリック・プゼナとティエリー・デシリーによるフィルムに見事に描かれています。
アフリカ大陸への往復は?マヌ・ディバンゴはそこで祝福され、哲学的にその栄誉を受け入れていますが、彼は騙されず、根拠のない批判や極論をかわす術を知っています。ジャーナリストが彼の稀有な政治的スタンスを非難すると、彼は茶目っ気たっぷりに、アートは彼が生涯をかけて取り組んできた大きな文化的コミットメントであることを思い出す。
カメラの前では、ベテランのミュージシャンが言葉を操っている。彼は自分の発言が取り上げられることを知っている。だから、彼は自分の言葉を相手に合わせる。トントンマヌ』はキャラクターのすべてを語っているわけではなく、この映画は主人公が見せたかったものの輪郭を描いているに過ぎません。この場合、彼の信奉者であり旅人でもあるヤニック・ノア、ウォーリー・バダルー、コートニー・パイン、オマール・ソーサの称賛に注目すべきかもしれません。彼らは短いコメントの中で、笑いが少なく、より深い人間性を持つマヌ・ディバンゴを愛情を込めて描いています。
ドキュメンタリー『トントンマヌ』監督:パトリック・プゼナ、ティエリー・デシリー(ボンヌ・ヌーベル・プロダクション/5.2.3.プロダクション)2021年-フランスの映画館で10月20日に公開
著:ジョー・ファーマー
https://musique.rfi.fr/musique-africaine/20211019-le-jazz-joe-tonton-manu